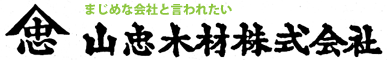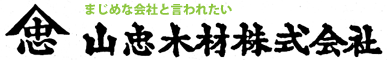|
(1) 合板工場群、深手負い苦境
岩手県、宮城県の海岸沿いに立地しているセイホクグループを中心とする合板工場群は大打撃を受け、国産材合板生産量の21〜22%を占めるため、当面の供給不足に加えて、今後の復興需要に応える面でも大きな痛手となっています。
製紙業界でも三菱製紙八戸工場や日本製紙石巻工場が水に浸かる被害があります。
(2011年3月30日 林業新聞社記事より抜粋)
(2) エネルギー政策見直し必至 − 衝撃与えた原発の爆発
注目を集める太陽光発電
積水化学工業住宅カンパニーが「太陽光発電実邸アンケート調査(平成22年度)結果」を公表しました。
光熱費の実績と太陽光発電装置の満足度と省エネ意識の変化などを調査したものです。
光熱費ゼロ住宅は73%(21年度は20%)で、大幅に増加しました。売電価格の上昇と装置の大容量化が要因です。
太陽光発電の年間光熱費収支は57,000円のプラスになりました。
太陽光発電装置採用の満足度は98%と非常に高くなっています。
理由は
光熱費が削減できた。
省エネ意識が高まったこと。
発電量や天気のチェックが楽しみになってきた。
です。
家族構成別の光熱費ゼロ率は、
夫婦世帯81%、夫婦+子供78%、子夫婦と親48%、子夫婦と子供(孫)と親夫婦43%です。
「電気使用量削減のために努力していることがある」という質問には98%の人が「ある」と回答しています。因みに一般の人は83%です。
日ごろの節電行動は
明かりを消す。
エアコンの冷房温度を高めにする。
エアコンの使用時間を短くする。
です。
「以前より節電するようになった」「深夜電力も利用」など節電行動が向上しています。
(2011年4月6日 林業新聞社記事より抜粋)
(3) 中古住宅取得の際は必ず耐震性の確認を
現在の中古住宅流通市場において、性能面を考慮しなくても取引が可能と思われている「築20年以内の物件」でも、約70%の案件で耐震性が不足しています。中古の木造住宅取得の際は、最低限耐震性の確認が必要なようです。
(日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 2011年4月6日林業新聞社記事より抜粋)
(4) 「森林法改正案」が可決 − 自給率50%へエンジン
復旧・復興資材の木材を早急に森林から伐採できるように修正し、必要な規定について施行期日を前倒しにすると明記しました。
(2011年4月13日 林業新聞社記事より抜粋)
(5) 床材用合板フル稼働 − 秋田プライウッド緊急増産
当面は一般住宅より復興需要への対応を優先します。
(2011年4月13日 林業新聞社記事より抜粋)
(6) 外国産材より国産材「8割」 − 森林資源の循環利用に関する意識・意向調査
農林水産省の平成22年に行なった調査で、消費者・林業者・木材流通加工業者を対象に実施されました。
消費者の生活に取り入れやすいと思われる国産材製品は「内装」と、8割の林業者・木材流通加工業者が考えています。
消費者が思う生活に取り入れたい木材製品は「家具」が40.7%で最多でした。内装は34.6%で2番目。以下、玩具・遊具、ガーデニング用品と続いています。
国産材と外国産材のどちらを使用する方が良いかを消費者に尋ねたところ、国産材のほうが良いとする回答が8割に達しました。
理由は、
1位 : 日本の森林を育てることにつながると思うから(約6割)
2位 : 地域の林業、経済の活性化につながる(55%)
3位 : 香り、安全性など性質、品質が外国産材より優れている(43%)
でした。
(2011年4月13日 林業新聞社記事より抜粋)
(7) 2月の新設住宅 − 持家や戸建分譲増加 貸し家は5ヶ月連続減少
2月の新設住宅着工戸数は62,252戸、前年同月比10.1%増加、9ヶ月連続の増加となりました。しかし、2月としては過去3番目の低水準でした。
持家、マンション、戸建分譲は増加しましたが、貸し家は減少です。
季節調整済み年率換算値は872,000戸で、前月比3%の増加です。
住宅床面積は前年同月比12%増、12ヶ月連続で増えました。
首都圏着工は前年同月比25.4%増、中部圏2.3%増、その他地域も5.8%増でしたが、近畿圏は3.6%減少しました。
持家が16ヶ月連続増加です。戸建分譲では首都圏が18.7%増加し、その他地域でも17.9%と大きく伸びました。
大阪の対前年同月比は21.2%増、和歌山1.7%増でしたが、兵庫22.8%減、奈良21.3%減、京都16.4%減、滋賀10.0%減となりました。
東京は48.0%増、愛知は10.0%増でした。
木造率は53.6%で、前月比0.3ポイント減少しました。
尚、住宅着工に仮設住宅は含まれていません。
(2011年4月13日 林業新聞社記事より抜粋)
(8) 国内針葉樹合板生産量予測
2010年の国内針葉樹合板生産量は、年間2,309,000m3でした。
12mm換算で 9,600,000枚/月 になります。
東日本大震災被災メーカー4社5工場の生産量は、
12mm換算で 3,300,000枚 です。
4月以降の全国国産製造工場の増産見込み数量は
12mm換算で 1,780,000枚 です。
つまり減少数量は、
12mm換算で 1,520,000枚(15.7%減)と予想されます。
今後、厚物(24mmなど)の生産比率が高まると思われます。
しかし、長尺合板は、実質的に生産能力のある工場は全国で1社しかなく深刻です。
ラワン合板は近々にも輸入品の入荷量が多くなってきます。9mm・12mmの品薄感は早期に解消されると思われますが、2.5mm・4mm・5.5mmの入荷量は今後も少なそうです。
(2011年4月13日 双日建材セミナーより)
(9) 住宅と木材あれこれ
需要者ニーズは何を求めているか
住選びの意向 在来工法による木造住宅 : 62%
その他の工法の木造住宅 : 22%
非木造住宅 : 15%
(内閣府「森林と生活に関する世論調査」平成19年度より)
木造率の推移 平成14年 : 44%
平成19年 : 48%
平成22年 : 57%
(国土交通省「住宅着工統計」より)
公共建築物等の木造化の現状
木造率 建築物全体 : 36.1%
公共建築物 : 7.5%
(平成20年度建築着工統計をもとに農林水産省において試算)
木材利用の教育環境形成効果
低温環境下における床面積の違いによる自覚症状の比較
眠気とだるさ 木造床 : 訴え率 約10%
コンクリート床 : 約14%
注意集中の困難さ 木造床 : 訴え率 約 4%
コンクリート床 : 約 9%
(文部科学省「早わかり木の学校」より)
(2011年4月15日 木材勉強会より)
(10) 仮設住宅建設が本格化 − 過去最大33,000戸
プレハブ建築協会は約3万戸を供給する計画。また、全国中小建築工事業団体連合会は2ヶ月で300戸を供給する予定です。
応急仮設住宅の建設要請状況(3月31日現在)
| 岩手県 |
8,800戸 |
| 宮城県 |
10,000戸 |
| 福島県 |
14,000戸 |
| 栃木県 |
145戸 |
| 千葉県 |
230戸 |
| 長野県 |
40戸 |
| 合計 |
33,215戸 |
(2011年4月20日 林業新聞社記事より抜粋)
|